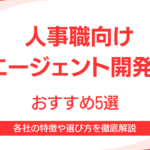AI活用研修「アローサル式Gemini研修」が現場で“本当に使える”理由
Google Workspaceに標準搭載された生成AI「Gemini」。
そのポテンシャルは計り知れませんが、「導入したのに現場で使われていない」「活用方法が分からない」といった声が多く聞かれます。
そんな企業の悩みに応えるのが、アローサル・テクノロジー株式会社が提供する「Gemini研修」。
今回は代表取締役CEOの佐藤拓哉氏に、研修の狙いと魅力について伺いました。
「そもそもGeminiって何?」という方は以下の記事をご覧ください。
▼関連記事

佐藤 拓哉
(アローサル・テクノロジー株式会社 代表取締役CEO)
一部上場SIerにてプロジェクトマネジャー、システムエンジニアとして5年弱従事。エンジニアリングの経験とグローバルに世界で挑戦するため、2013年9月アローサル・テクノロジー株式会社を創業。
ベトナム、バングラデシュのオフショア地域にてWeb/AI事業グレーション事業を推進し、システムやAIを活用した事業開発のスペシャリストである。のべ20,000名への生成AI活用研修実績をもち、満足度97%超えの研修を設計。
Gemini研修とは?誕生の背景と概要
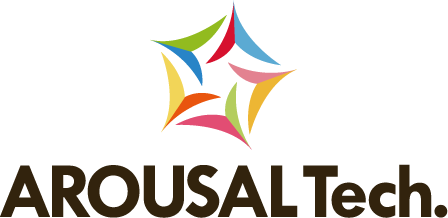
 本城
本城まずは「Gemini研修」について教えていただけますか?



はい。簡単に言うと、GoogleのAI「Gemini」を業務に実際に活かせるようにするための研修です。
Gmail、スプレッドシート、ドキュメントといった日常業務で必須のツールとGeminiをどう連携させるか。
さらに、プロンプト設計の方法、注意すべきセキュリティ観点、そして活用のコツまで、体系的に学べるプログラムになっています。



なるほど。まさに“現場で使える”ことを意識された研修なんですね。



そうなんです。しかも対象は幅広く、非エンジニアの現場担当者からマネジメント層、AI推進担当者まで。
特にバックオフィス業務では、数時間から数十時間単位の効率化につながる可能性があり、現場に直結する効果が期待できます。



ただ、GeminiってもともとWorkspaceに標準で入っているのに、意外と知られていないですよね。



おっしゃる通りです。実際、多くの企業がGoogle Workspaceを契約しているのに「Geminiを搭載していることすら知らない」という状況が珍しくありません。
しかも、3月に料金が大幅に上がったにも関わらず、使いこなせていないのが現実です。“宝の持ち腐れ”になっているんですよ。



その現実を見て「これはなんとかしなければ」と思われた?



はい。もともとは社内で「Geminiをちゃんと使えるようにしよう」というところから研修を設計しました。
ところが、それが想像以上に効果的で。社内で得た知見を体系化して、外部企業にも提供する形に整えたのが現在のGemini研修です。



まさに“現場の声”から生まれた研修なんですね。



ええ。AIを入れただけでは企業は変わらない。実際に現場で使えるようにしてこそ初めて意味がある。そのためにGemini研修を商品化しました。
▼関連記事


仕組みと提供スタイル:柔軟な形式と充実のフォローアップ



実際の研修は、どのような形式で行われるのですか?



大きく分けると、集合研修とeラーニングの2パターンがあります。
集合研修はオンラインでも対面でも対応可能で、2日の短期集中型もあれば、集合研修とeラーニングをベースに各社の課題に合わせて柔軟に設計します。



現場の担当者とマネジメント層では、求められる内容が違うと思いますが?



はい。研修は受講者のリテラシーや役職に合わせてカスタマイズしています。
例えば現場担当者には「業務効率化に直結する操作スキル」を、マネジメント層には「チームにどうGeminiを浸透させるか」という観点を重視します。



確かに、それぞれが同じ目線で学ぶのは難しいですよね。



そうなんです。そこで導入しているのが「選抜研修」です。
社内の選抜メンバーに向けて活用研修を行い、実務での活かし方を強化します。
研修の成果と受講者の声:具体的な事例と97%以上の満足度
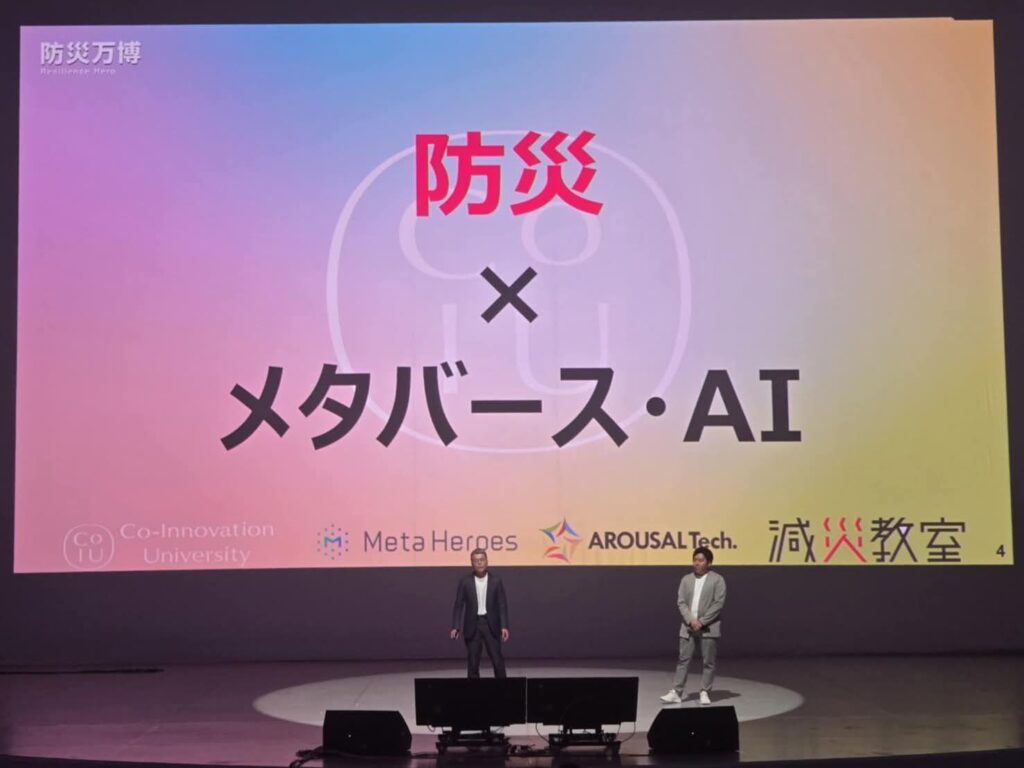
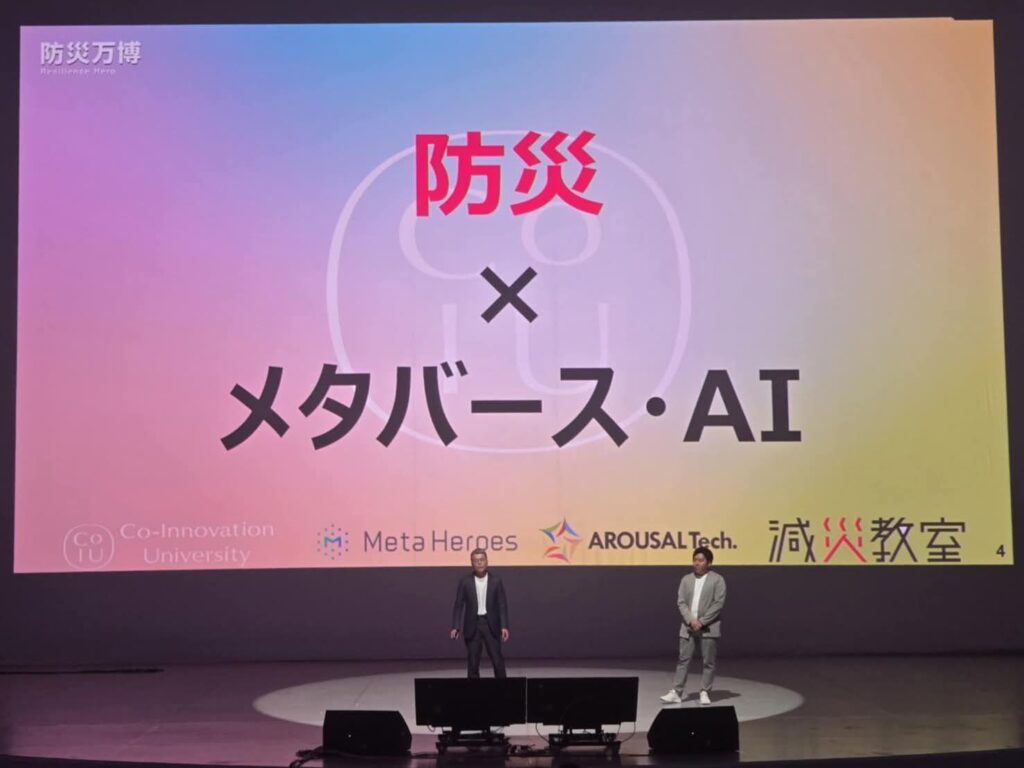



研修を導入した企業では、どのような成果が出ていますか?



不動産会社の事例を紹介します。
物件ごとに膨大な議事録があり、その中から特定の修繕履歴を探すのに毎回80ページ以上を読み込んでいたんです。
研修を受けてGeminiを活用したところ、一瞬で必要な情報を抽出できるようになり、作業時間が劇的に短縮されました。



それは大きなインパクトですね。



受講者の声も印象的です。「これまでの作業が何倍も早くなった」「AIがこんなに身近で使えるとは思わなかった」といった反応が多いです。
特にAIに苦手意識を持っていた方ほど、“自分でも使えるんだ”という自信に変わっています。



満足度も高そうですね。



はい。全体で97%以上の満足度をいただいています。
さらに、受講者のAI活用度が3割程度から7割近くまで跳ね上がるケースも珍しくありません。
他社との違い:実務直結の設計思想と経験豊富な講師陣





AI研修を提供する企業は増えていますが、御社ならではの強みはどこにあるのでしょう?



一番の違いは、「驚き」や「好奇心」を引き出す設計です。最初から堅苦しい理論ではなく、Geminiに熊本弁でしゃべらせてみたり、歌を作らせたりすることで「もっと使ってみたい」と思わせます。
そこから業務活用へ自然に導入していくんです。



ただ知識を教えるのではなく、体験から引き込むんですね。



そうです。そしてもう一つ大きな違いは、実務に精通したエンジニアが講師を務めていること。
私たちは普段からGeminiを業務で使っているので、机上の理論ではなく“明日から使える”ノウハウをお伝えできるんです。



単なる“研修会社”ではなく、“AIを実際に使っている会社”だからこその説得力ですね。



ええ。私たちは現場使用経験が豊富な講師が設計・登壇し、実践からのノウハウを反映しています。これが他社との差別化要素になっています。
Geminiを学ぶ価値と今後の展望





最後に、ChatGPTなど他の生成AIと比べて、Geminiならではの価値をどう見ていますか?



まずはGoogle Workspaceとの統合性です。すでに業務で使っているツールに自然に組み込めるので、学んだらすぐに業務改善につなげられる。
しかも標準搭載のため追加コストを抑えられる点も魅力です。さらに処理できる情報量が大きい点も強みですね。



なるほど。精度や安定性の面でも信頼できそうです。



はい。特に「業務でミスなく正確に使いたい」という企業にはGeminiが向いています。



今後の展望についても伺えますか?



現在の課題は講師リソースの不足です。研修の質を維持するために、私と同じレベルで講義できる人材を育てていく必要があります。
AIは日々進化していますから、私たち自身もアップデートを重ねながら、企業のAI活用を長期的に支えていきたいですね。
まとめ
アローサル・テクノロジー株式会社のGemini研修は、Google Workspaceに眠るAIポテンシャルを最大限に引き出し、「導入したけど使われない」という壁を突破する実践型プログラムです。
社内の実践から生まれ、20,000名以上の研修実績、97%以上の満足度、さらにGoogle Workspace導入支援まで一気通貫で対応できる強みを備えています。
Geminiを業務に活かし、AI時代を乗りこなしたい企業にとって、最良の選択肢となるでしょう。
▼Gemini研修の相談はこちら
https://www.arousal-tech.com/inquiry
関連記事: